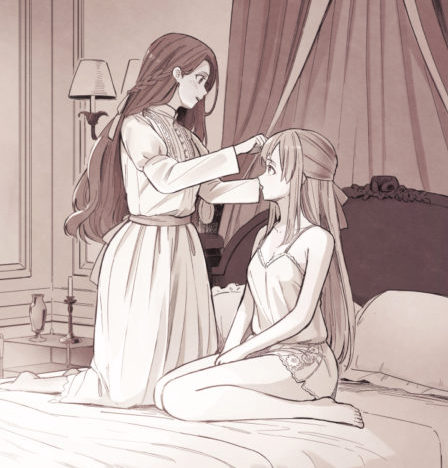『フラニーとズーイ』の読書考察。純粋で神秘化していない現実的キリスト教宗教哲学の巡礼物語

J・D・サリンジャーの短編小説『フラニーとズーイ』についての考察
『フラニーとズーイ』はJ・D・サリンジャーによって書かれた小説であり、一般的な紹介では青春小説であるとされる。また、青少年の自意識だとか、世に蔓延するエゴ、あるいはそれらへの向き合い方がテーマであると言う。
しかしながら、私はそうしたことは表層的な道具立てであって、あるいは広告宣伝のために拵えられた売り文句にすぎず、作品の中核ではないと考えている。
これはあくまで「キリスト教の信仰」についての書であるし、とりわけ、なんらかの創作者── 行動者と言ってもいい ── が陥る信仰的な悩みについてのサリンジャーの回答の書である。*
*またはキリスト教の、それもキィルケゴールがいうところの、単独者としてのキリスト教徒的回答である。
前提理解に必要な知識
まず、この作品を語るうえで目を通すべき考察などを寡聞にして存じないことについては申し訳ない。
ただ幾つかの感想や考察、ネット上で読める小論などは読んだが、「文学的に読んでみた」という前提があるために、日本人が苦手とする宗教哲学からの視座がすっぽり抜け落ちているように感じる。これでは物語の本質が分からないのではないだろうか。
少なくとも、ストア主義、聖書(旧約の基本知識および伝道者の書・新約の四福音書・手紙類)、トマス・ア・ケンピス、バニヤンの『天路歴程』、エックハルトかタウラー(ドイツ神秘主義)、老子、歎異抄あるいは鈴木大拙の著作あたりの、ベースになっている思想に一通り自身で触れて、実際に経験としてそこにある宗教的悩みと、思想的解決策を自身が共有しなくてはならない。
親切にもサリンジャーが作中でそれらをきちんと登場させてくれているのだから、「そっち読んでねサイン」と解するべきだろう。
しかしもちろん、この作品を単に娯楽作品としてのみ楽しみたいならば、別に前提理解など不要で、サリンジャーの文章や構成、村上春樹氏の訳文のかっこうよさを楽しめばいいだろう。そんなことは当然である。この記事はあくまで、そうじゃない場合に向けて書いている。
ちなみに、作中に出てくる本は『無名の順礼者―あるロシア人順礼の手記』であるようだが、これは作中で説明される内容で充分だろう。

畸形人形という疎外感を見落とさないために
さて、なぜそんな前提書籍が小説にあるのかと言えば、その宗教哲学、思想的なベースがないと、フラニーとズーイの議論で問題とされている悩みも、その回答も理解できないからである。
もしそれらの前提を理解しないで読んだ場合にどうなるかと言えば、「思春期の悩みと独善」という、お決まりのテーマしか浮かび上がってこないのだ。
より登場人物の主観的に言うなら、一種のヒステリーや、感受性の強すぎる宗教熱心、今風に言うなら中二病的悩みだと括られて、周囲からは── 作中では主にフラニーの彼氏と母親から ──「何をそんなに」と雑解釈をされるということだ。
これはすなわち、ズーイが自分達を「畸形人形」と評したように、宗教的理想を持って生きる自分たちが世間的に理解されていないという疎外感である。そして、それを受け入れて畸形人形として生きるズーイは、キィルケゴールの言う単独者なのだ。*
*もちろんサリンジャー自身もそうである。
さらに言うならば、この書籍の恐ろしいところは、まさにこの物語において描かれる「創作(俳優としての演技を含む)における本質の理解されなさ」という悩みを問題として取り扱いながら、実際にこの書籍自体も、多くの人には表層の楽しみだけを見せて、本質は理解されえないままに、畸形なままに書かれているという点にある。*
*並みの作家ならそれでいて世間に大ヒットとして評価されるものに仕上げることは出来ないだろう…
厭世主義を超える価値観
物語の創作 ── 作中ではフラニーとズーイの俳優としての演技 ── と言う過程で、二人が直面した問題は、端的に言えば「人間は何をしてもエゴからしか何もし得ないのではないか? そして、それらは全て無価値な塵にすぎないのではないか」ということだ。
こうした厭世主義的な考えは、ニーチェやショウペンハウエルなどを引き合いに出すまでもない。伝道者の書でとっくに語られて、かつ以下引用文のように肯定されている。*
ヘベル、ヘベル。一切はヘベルである。**
伝道者の書1の2
*ほかに伝道者の書2の11、2の22、4の4も同じことである。
**日本語ではヘベル=空と書かれる。הבל ヘベルとは蒸気や煙を指す言葉で、そのように捉えどころがなく、消え去るものということ
しかし、物語の本質は、そうした厭世観を超えていく術について、キリスト教の教えをベースに語ることにある。
ニーチェは超人思想をぶち上げ、仏教やショウペンハウエルはそのまま受け入れよとした。キリスト教は信仰によって突破を試みるのである。
結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。
伝道者の書12の13
神を畏れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。
これだけを抜き出すと非キリスト教徒が腹立たしく思うことは想像に難くない。
カルト的で横暴に聞こえるだろうし、人間個々の尊厳を無視しているように感じるのだろう。しかし、それはキリスト教以外の宗教も含めて、宗教的本質を理解せずに言葉だけ受け取ってしまった場合の誤解である。
すべてのまっとうな宗教的探究は差違を、目くらましのもたらす差違を忘却することへと通じていなくてはならないんだと。
『フラニーとズーイ』 新潮社文庫 P101
まさしく、宗教的本質の話であるこの部分は、キリスト教に限らず、禅や仏教(主に鎌倉仏教)に通ずる部分が存在している。これはサリンジャー自身が、当時アメリカで流行した東洋思想にも傾倒した経験から来ている。
そしてまた、それらに一種の幻滅を抱いてキリスト教に回帰した経験も強く作用しているだろう。

無に沈み、それから希望を得る
ドイツ神秘主義、エックハルトの継承者であるタウラーはこのように説く。
常に自分の無の悟りを目的とし、熱心にそれに達しようと努めれば、
ヨハネスタウラー説教集1 P61
大いに救われることになります。内面あるいは外面で
自分の思い上がりに気づいた場合は、ただちに最深の「底」へ、
躊躇しないで速やかに沈まなければなりません。
あなたは「底」の中で、自分の無へ沈みなさい。
まるで東洋思想のような宗教哲学だ。つまり、自身が無であることを知り、受け入れ、そこに沈む。その前提があって、一度自分から無になって(その認識に戻って)から「神に聞き従う」につながるのだ。
実を言うと、カルトにせよ、まっとうな宗教にせよ、ここまでは同じである。洗脳か洗礼かの違いしかない。しかし、その無になった個人と言う器に何を注ぐか、その一点に差異がある。
カルトであれば教祖や団体への帰依とか金であろう。分かりづらく危険なのは「救い」だの「愛」だのと言う連中だ。*本来のユダヤ・キリスト教は「希望:どんな時も喜びうること」、「神の霊」と言われるものをを注ぐ。
*キリスト教界の問題は、教会の発足した時代からずっと、カルト的な派閥が混在し続けているということにある。しかし同時に、それを根絶やしにしようという独善的正義感から何が起きるかを現代に生きる私たちは知っている。
基本的に宗教の危険性というのは、一度個人を無にするということと、(神に)聞き従うようにするという部分にある。
その為、信仰に入るためには人に流されたり、当然ながら強制されたりしてはいけない。また、苦境に立って初めて、信仰から得られる宗教的利益を求めて縋ってはいけないのである。*なぜなら、そうすると容易に聞き従う相手を神から人に替えてしまうからだ。
*伝道者の書12の1 あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。
話が遠回りしたが、まさに作中においてフラニーは厭世観と宗教的傲慢 ── 及びそれに気づいた自己嫌悪 ── の虜になって苦悩する。ズーイが最終的に解決策として提示したのは、本作にある通り「太ったおばさん」。すなわち、キリストへの回帰の道である。

何のために自発的な行為を行うのか
創作者のキリストへの回帰の道と上に書いたが、実を言えば創作者である必要すらない。
はたらき(仕事に限定されない)を何のためにするのかという虚しさに突き当たった全ての人々にとって、これは共通の回答として提示されたのである。
全ての人と言っても、その解決方法が機能するのはキリスト教徒のみで、それも真に信仰を会得したキリスト教徒向けではあるけれど…。*
*だからフラニーが間違った信仰の「脇道」や「躓き」に見舞われるのだ。彼女の役どころは反面教師だ。彼女の失敗は、ただ祈りの言葉を何度も唱えることで「お手軽神秘体験」を得ようとすること、イエスの言葉やアイデンティティから気に食わないところを取り除いて偶像化する試みなどがそれである。バニヤンの『天路歴程』はこのあたりをメインテーマとして扱っているけれど、この物語ではサリンジャーがそれの焼き増しを目的としているようには思われない。あくまでこれも道具立てであろう。
その回答がどのようなものか、それはもちろん。この作品でおそらく最も有名なフレーズに現れている。
シーモアの言う太ったおばさんじゃない人間なんて、誰ひとりいないんだよ。*
『フラニーとズーイ』新潮社文庫P290
*太ったおばさん=キリスト(キリスト・イエスに限定されない)
ここはサリンジャーのキリスト理解が、いささか汎神論に傾いているのではないかと怪しい部分であるが、おそらくそうではないであろう。また、ここで言うキリストはキリスト・イエスのことだけでなく、もっと広範なあらゆる宗教的救いの本尊とでもいうべき概念だろう。
ズーイがこの言葉に至るまでの文脈を追い、かつ前提知識を合わせるなら、回答の解釈はすなわち、「神の意ゆえにはたらきをし、神を思ってはたらきをせよ。自らのはたらきのうちに福音が生きていることを喜んで、自発的に自身の労苦を負え」ということだ。
これは一種の義務感や使命感にあたるもので、そうすることで地上の人間からの反応や賞賛、地上の財宝を無意味なもとのすること、また自身のエゴからも自由になり得る”システム”であることを説いている。
またこれは、本当に人間を変えうる力を持つのは、上なるものへの奉仕的活動、軍務的活動であるという考えからくる。*そして、「上なるもの」つまりは神を、会社だとか国家に挿げ替えられないようにしなくてはならないのである。**
*カール・ヒルティ『幸福論』第三巻 岩波文庫 P246 : 「(キリスト教は)その本質に存する軍人的なものが発揮される。(略)自分の勤めが分かっている場合に、なおも思案に暮れることは許されない。」
**日本をはじめ多くの現代的問題はここにあるのだろう。人を神としてしまったり、会社や国家、あるいは何らかの理念を神としてしまった時にブラック企業問題や過剰なナショナリズム、過激なリベラリズムが立ち上がる。人間はとかく偶像崇拝をしやすい。
サリンジャーの回答と、他の考え方。宗教的調和の本質を見据えて
すべての人の中に「太ったおばさん=キリストのかたち」が存在すると言うサリンジャーの見解は、先に述べた通り少し汎神論的であるが、旧約聖書的だとも言える。── つまり人は神の形につくられたというやつ ──
あらゆる宗教を包括しうる解釈としての回答を試みたのだろうと思う。しかし、私はこれに違和感を抱く。なので、本作の考察とは別に、違う考えがあることを書いておきたい。
以下は私が愛読するヒルティの一節だ。*
われわれが人間を愛さねばならないのは、彼らが愛に値するからではない。(略)むしろただ愛することによってのみ、互いに損なうことなく人間と生きることができるからであり、また、人間と共に生きることは神の意志だからでもある。
『幸福論』第三巻 岩波文庫 P270
*おそらく彼は19世紀に生き延びたドイツ神秘主義の最後の継承者だろうと思う。
サリンジャーの回答(キリストの遍在)は無理だ。と私は思う。すべての人のなかに神の姿を見出すのだという導きは、汎神論がベースの日本人的には理解しやすく、いっけん良いもののようだが、実際には使い物にならないだろう。
それよりは、神の性質であるただ愛することを、「シェマ」にある通り、*それを命令として聞き従うことに決める方が、ずっと実現可能ではないだろうか。
*シェマ:第一の掟。聞けイスラエル。私たちの神、主は唯一である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟。隣人を自分のように愛しなさい。
あなたが嫌いな人間のうちに良い人間を見出して、それだけを見てあげよう。なんて物分かりの良い、お行儀の良い言葉よりも、「好き嫌いを捨ておけ、お前はそいつと今戦場にいて、同じ銃座を守っている。そいつと否応なく協力して、そいつの手助けをして、そいつを思いやって行動してやらねばならない」という軍務的な行動規範に縛られた方が、いや、そうすることでしか、そも人間全てを愛するなど不可能なのだ。と私は思う。
私はそう言うヒルティに賛同しているし、何より福音書のイエスもこんなノリである。*
*特にマルコ福音書は実践的なのでその傾向が強い。マタイはもっと律法的。ルカは初心者向けなのでもっと優しさや憐み深さが前面に出てきており解説的。ヨハネは特殊で信徒向けの神秘性が強い、最も信仰的書である。フラニーの犯した過ちはイエスのやさしさと憐み深さだけを抜き出そうとした行為である。
しかし、もちろんサリンジャーの意見に賛同する人もたくさんいるだろう。おそらく多神教が大好きな人や、私よりも人を好意的に信じられる人だと思う。それはそれで何の問題もない。
なぜなら兎にも角にも、見解の差違は忘却しなくてはならない。本質にあるべきは「宗教的な到達の先に、全ての人に対してまずは好意的に向き合う性質を持つこと」なのだと理解すればよいだろう。*
*キリスト教徒において、マタイ5章43節を引用して、すべての人を愛さねばならないかのように理解する人が多いが、それは違うだろうと思う。聖書にも明確に敵の存在は描かれるからだ。「神すらも赦したまわぬ罪」を犯した者を、人が赦すようには言われていない。これもまたフラニーと同じ失敗だ。あくまで「まずは」すべての人に好意的に親切に、寛容に向き合うこと。また「本心から悔い改めた者は」赦すこと。ルカ22章51節にて、イエスを捕えに来た兵士の耳をペテロが切り落とした時、イエスはペテロを制止して「もうそれでよい」とは言ったが、叱責はしていない。つまり、敵であるというプロフィールから愛さなくてもいいとはならないが、実際に敵となった者に対しては対処することは当然ありうることとして解されている。もちろん、そのうえでイエスが兵士の耳を癒されたように、敵に憐みを持つようにとも書かれている。聖書の本質を理解するためには、こうした繊細なバランス感覚をくみ取らなければならない。

ラブストーリーにおけるラブの定義
最後に、この物語がラブ・ストーリーであるとする解釈に対しての同意と異論を記したい。
私が今からお目にかけようとしているのは、短編小説と言うようなものからは程遠く、むしろ散文によるホーム・ムーヴィーに近いものである。
『フラニーとズーイ』新潮社文庫P72
私がここで提供しようとしているのは実を言えば、神秘的な物語でもなければ、宗教的に神秘化された物語でもない。言わせていただければ、これは習合的な、ないしは複合的な、そして純粋にして入り組んだラブ・ストーリーである。
『フラニーとズーイ』新潮社文庫P75
これらは冒頭で作者が「ズーイ」の挨拶の中で語っているのだから、ラブ・ストーリーではあるだろう。
しかし、「ラブ・ストーリー」と聞いて「Love」を「恋愛」だとか「愛情」という個別差別的な誰かに対する感情として認識してはいけない。それは単純に翻訳からくる誤読である。
イエスの言う「ラフマー」→「アガぺ」は「自分よりも他人の益になることを追い求める選択。そうした行動」をさすような、「親切」だとか、カント的な「自律的な善い行い」に近い感覚である。*
*カントは前提書籍に上げていないが、『道徳形而上学原論』および『実践理性批判』については深い関連がある。また、アダムスミスの『道徳感情論』もだが、いずれも宗教性を排した道徳哲学性が強く、本書の前提としてはやや広範過ぎるように思って外した。
ゆえに、このお話は習合的で複合的で、純粋にして入り組んだアガぺの話だ。
サリンジャーがなぜアガぺと言わなかったのかは分からない。私の考えが完全に的外れなのかもしれない。でも私は、単に「アガペ」という言葉に付随してしまう神秘性を、キリスト教に限定する宗教的専門用語性を、物語に込めたくなかったんじゃないかと思う。
この物語はとても現実的で、現実の世界で地に足を付けて歩いていく、東洋の思想にも強く影響されながら、キリスト教宗教哲学の実践をしていこうとする二人の若い兄妹が、悩みとその解決に至る、そんな巡礼の一幕なのだから。
作品背景と宗教臭いという批判について
私は新潮社文庫の村上春樹訳版で読んだ。私は訳文に対する知識を持たないけれど、非常に軽妙で、かっこいい訳だと思う。いい仕事なのだと思うし、敬意を表することに異存ない。
ただ村上氏が、あとがきは作者の意向で付けれないからと、「基本情報を提供する」という名目で入れたエッセイの紙切れは良くない。*
*サリンジャーはまえがきやあとがきを入れるな。本文以外を付け足すな。と言っていたそうだが、まったく晴眼だ。
もちろん宗教性の強さも、当時のサリンジャーが東洋宗教へ傾倒したことも、新興宗教的キリスト教科学に熱心だったことも事実ではあるが、そこから発露されたこの物語は、それによって損なわれたものなどない。
表層の娯楽性すらも減じてはいない。それは広く受け入れられた事実に表れているだろう。もし減じていると思うならば、それは単にその読者の「宗教嫌い」が原因であって、作品との相性の問題だ。作品の内容的質を貶めるようなことを言うべきでない。
むしろ、私から見ればこの作品の面白味はまさに「宗教的本質を理解しようと努めた人間の成果物」である点にある。
誉めそやされている文体なんぞは、作中で言われている、文学的で、表層の「ちゃらちゃら」した「才知が勝ち過ぎている」ものでしかない。むしろそうした技巧的な側面は、サリンジャーを作家としてもてはやす世間に対しての皮肉だ。「磨いた靴」の方を見なくてはならない。
当時確かにアメリカに吹いた東洋思想への傾倒、それを作家自身も実践し経験し、苦悩と幻滅を経て、ついには正統的キリスト教の教えに立ち戻ろうとする過程に彼はあった。
そうしたなか、他宗教の内にある信仰の本質をも認めるという、当時始まったばかりのエキュメニカル運動的な視座を、物語という形に築き上げた傑作であることに、私は称賛を送らねばならない。*
*エキュメニカル運動とは、キリスト教の諸教派一致運動のこと。『フラニーとズーイ』出版の翌年1962年に、第二バチカン公会議によって成果を上げ、現代のキリスト教における大きな潮流となっている。
不遜にも彼の作品にエッセイの紙切れを挟むのなら、彼の生きた時代的状況の上っ面だけを知識として取り入れて、知った風に書いたり、文学的な娯楽作品、商業作品としてしか見ないような態度を超えて、また、そうした志向性をもった作家であるというろくでもない分析ばっかりをしていないで、真摯に彼のしようとしたことに目を向けて欲しいものである。
最後の最後に
これで本当に最後に、作中から三つ、聖書から一つの箇所を引用しておえる。
演技をするんだ、ザカリ―・マーティン・グラース。*いつでもどこでもおまえが望むままに、そうしなくてはならないとおまえが感じるのであれば。
『フラニーとズーイ』新潮社文庫 P103
*ズーイの本名はザカリ―。本文でもなんの説明もなく出てくるから混乱する…
つまり俳優である限り君は演技することを要求されているんだという事実すら、君がいまだに分かっていないのだとしたら、こんなことを話しまくって、いったい何の意味があるっていうんだ?
『フラニーとズーイ』新潮社文庫 P287
でもとにかく靴は磨くんだ、と彼は言った。おまえは太ったおばさんのために靴を磨くんだよ、彼はそう言った。(中略)とにかく、シーモアがどうしてあの番組に出る前に僕に靴を磨かせたのか、はっきりとわかった気がした。それは筋のとおったことだった
『フラニーとズーイ』新潮社文庫 P289
新約聖書ルカによる福音書5章5節から。イエスがシモン(ペテロ)に漁をするように言ったあと。
シモンは「(イエスに対して)先生、わたしたちは夜通し苦労しましたが、何もとれませんでした。しかし、お言葉ですから網を降ろしてみましょう」と答えた。
新約聖書ルカによる福音書5章5節
「人間は何をしてもエゴからしか何もし得ないのではないか? そして、それらは全て無価値な塵にすぎないのではないか」という問いに対する答え。それは、
信仰者は自身の無を知り、その召命に応じて、それぞれのはたらきを、そのはたらきそのものの為に、あるいはそのはたらきをする他者のために。そうして、神を観客として、自発的に行わなければならない。その労苦のなかにこそ福音が生きている。そう回答したのではないか。